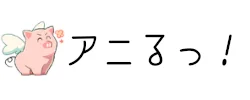評価 ★★★★★(81点) 全12話
あらすじ 後藤ひとりは動画投稿サイトで評判のギタリスト「ギターヒーロー」の名で活動する少女だった引用- Wikipedia
全ての陰キャに捧ぐ
原作はまんがタイムきららMAXで連載中の漫画作品。
監督は斎藤圭一郎、制作はCloverWorks
ぼっち
主人公である「後藤 ひとり」はいわゆるボッチな女の子だ。
そのぼっちさは筋金入りであり、幼稚園の頃から彼女は
「他者」の輪の中に入ることができないまま中学生になっている。
自分にはなにもない、陰キャでぼっちな自分には何もないと感じていたある日、
彼女は音楽番組に出ていたアーティストの言葉をきっかけにギターを始める
「バンドは陰キャでも輝けるんで」
そんな些細な一言が彼女の人生を変える。
「バンド組んだら私みたいな人間でももしかしたら輝ける?」
陰キャであることも、ぼっちなことも自覚している。
それでいいと思いつつも彼女の中にも「承認欲求」がある。
バンドを組んでちやほやされたい、輝きたい。
子供の頃から人の輪の中に入れず、友達も居ない。
そのことを彼女は自覚しつつも、変えたいと思っていることを感じさせる台詞だ。
人は一人では生きていけない。
家族以外の「誰か」を彼女は心の何処かでは求めている。
だからこそ彼女はギターを掻き鳴らす。
ギターを始める切っ掛けは人によって様々だ。
だが、誰しも「誰かにきかせたい」という自己表現の思いがあり、
同時に「モテたい」という気持ちもあるはずだ(笑)
学園祭でライブをする、思春期の少年少女なら誰しも
「妄想」したことはあるはずだ。
しかし、人生はうまくいくもんじゃない。彼女はギターを掻き鳴らす。
毎日6時間練習し続けたものの、
友達はできず、バンドも組めず、学園祭に当然出れるわけもない。
彼女は淡々と「弾いてみた」動画をアップロードする日々だ(笑)
それもまた自己表現と承認欲求を満たすためのものだ。
ネット上では「ギターヒーロー」として
登録者数は3万人超えているものの、
いつのまにか高校生になり、自己承認欲求をこじらせ、
陰キャもぼっちもこじらせている。
誰かに話しかけてほしい、誰かとバンドがしたい。
だが、彼女が自ら誰かに話しかけるわけもなく、誰も彼女に話しかけない。
ぼっち極めれり、陰キャ極めれり。
1話の序盤は彼女のこの徹底した「陰キャ」ぶりを描いており、
それが「後藤ひとり」という主人公の魅力と可愛らしさ、
ぼっちぶりが多くの視聴者の共感を誘っている。
そんな彼女に「伊地知 虹夏」が話しかけることで物語が動き出す。
陽キャ
「伊地知 虹夏」という少女は陽キャだ。
公園に一人たたずんでいた主人公に話しかけ、
あろうことか「バンド」の臨時メンバーに誘う。
陽キャとは裏を返せば「パーソナルスペース」を意識しないものだ。
人間一人一人がもつパーソナルスペース。
その「壁」が陰キャは分厚く、分厚いがゆえに他者の
パーソナルスペースにふみこむことができない。
しかし、そんな「ぼっち」な彼女の分厚いパーソナルスペースを
「伊地知 虹夏」という少女はあっさりと貫く。
名前を聞けば下の名前ですぐに呼び、
見ず知らずの少女をギターを持ってるからという理由で
臨時メンバーに誘う始末だ。
主人公の陰キャさとはまるで正反対の陽キャぶりを
初登場シーンからガンガンに感じさせ、主人公とのキャラのギャップがたまらない。
自信
主人公の中には「自身」が少なからずある。
中学生の時から毎日6時間練習し続け、登録者3万人もいる。
だからこそ自分のギターはうまい、バンドをやれるはずだという認識がある。
それが彼女の中の唯一あるものと言っても過言ではない。
しかし、あっさりとそれが打ち壊される(笑)
バンドはバランスだ。
ソロでギターを弾くことと、バンドでギターを弾くことは
同じ「ギター」を弾くという行為でも違う。
ドラムの音を聞き、ベースの音を聞き、自分の音を出す。
誰かが走りすぎればあっさりと曲のバランスも崩れてしまう。
ギターの技術はある、だが、彼女には「他者」とつながる技術がない。
「バンド」を組みたいという思いはある。
それでも、その思いだけではどうしようもない。
しかし、その思いを二人の少女が掬ってくれる。
「ギターヒーロー」として3万人の登録者がいる彼女。
そんな登録者が目の前にいる。
自分をギターヒーローと知らずに、ギターヒーローのことを褒めてくれる二人。
ずっと一人で頑張り続けてくれた「自分」を褒めてくれる、
今まではネット上だからこそ「見えなかった」視聴者が、
目の前に居て直接言葉を告げてくれる。
だからこそ彼女は素直に「バンドをやりたい」と言い放つ。
ぼっちで陰キャな彼女の小さくとも大きな一歩だ。
自らの意思を誰かにストレートに伝える、
家族以外に初めてできた「交流」だ。
今日だけじゃない「次」もある。
誰かと「演奏」することの楽しさを彼女は
「ダンボール」の中で噛みしめる(笑)
このぼっち陰キャギャグとバンド活動のまじめさのバランスが素晴らしく、
見れば見るほどキャラクターに愛着を持ちニヤニヤしてしまう。
バイト
この作品は非常に「生々しく」バンド活動というものを描いている。
彼女たちは別に売れっ子なバンドなわけでも、
最初のライブで大人気になるわけでもない。
あくまでも女子高生が組んだばかりのバンドにすぎない。
しかし、ライブハウスでライブをしたい。
そのためには「お金」がかかる。現実的だ。
ライブハウスでのライブにはバンドごとに「チケットノルマ」があり、
自分たちで客を呼べなければ売れなかったチケットの分は「自腹」だ。
ゆえに稼がないといけない。
この作品とやや似たような作品として「けいおん!」を
思い返す人も多いかもしれないが、この作品の方向性はけいおんとは違う。
けいおんはあくまで「日常部活」ものであるが、
この作品は「日常」ではあるが「部活」ではない。
ギターを買うためにバイトをしていた「けいおん!」とは違い、
この作品はライブをするためにバイトをしなければならない。
似たように見えて方向性がまるで違う。
特に「主人公」のぼっちさと陰キャさは「けいおん!」には
一切なかったものだ(笑)
ようやくバンドメンバーと少し会話ができるようになったのにも関わらず、
バイトを通じてもっと多くの人と関わらないといけない。
バイトを休むために風邪をひこうとしたり、
そもそもライブハウスに一人で入れなかったりと、
彼女のぼっちさが共感と愛くるしさを生んでいる。
ライブハウスでのバイトを通じて
「ライブハウス」というものがどういうものなのかを視聴者にも説明しており、
アマチュアバンドあるあるやアマチュアバンド活動がどういうものなのかというのを
この作品は自然に描いている。
ライブハウスでのバイト活動の中で他のバンドのライブを見て彼女は感じる。
自分の最初のライブがいかにひどかったか、自分がどういうライブをしたいのか。
不器用でぼっちで陰キャな彼女が自分なりに「笑顔」で接客しようとする様は
ギャグシーンではあるものの、どこか涙腺を刺激される。
喜多 郁代
彼女はもともと結束バンドとしてやっていくはずだったメンバーだ。
しかもボーカルという重要なポジションにいながら当日ぶっちしてしまう。
その原因は彼女がギターを弾けるという嘘を言ってしまったためだ。
同じバンドの「山田 リョウ」に憧れ、自分自身もバンドをやりたいと思う。
シンプルな理由だ。だが、彼女もどこかおかしい。
憧れという感情をこえた、百合な感情とも違う。
バンドという家族になることで、「山田 リョウ」の家族になりたいと思っている。
意味不明である(笑)
ギターも弾けず、1度は逃げ出してしまったからこそ
彼女たちのバンドである「結束バンド」に入る資格はないと思っている。
だが、そんな彼女を主人公である「後藤ひとり」が引き止める。
彼女の手を触り、彼女の事情を知ったからこそ、
自分と同じように「努力」したことを感じてしまう。
そんな彼女を引き止める姿は1話の彼女ではあり得なかったことだ。
伊地知 虹夏に声をかけられ、彼女と山田 リョウとともに
「結束バンド」というバンドを組み、バイトを始めたからこそ、
彼女を引き止めることができた。
1話から3話という序盤で結束バンドというバンドが形になり、
「後藤ひとり」という主人公が少しだけ成長する。
一人ひとりのキャラクターを丁寧に掘り下げ、愛着をもたせ、
徐々にバンドとして形になっていく彼女たちの姿に愛おしさすら感じる。
歌詞
そんな少し成長した彼女に重要な任務が与えられる
オリジナル曲の歌詞作りだ。
結束バンドがバンドはコピーバンドから始まり、
ようやくバンドとしてのオリジナル曲づくりに没頭する。
だが、難関だ(笑)
中学生の頃に書いた黒歴史歌詞ノートを引き出してみたり、
現実逃避してみたり、歌詞をひねり出そうとするものの
なかなか歌詞をひねり出せない。
この葛藤も「後藤ひとり」という主人公だからこその台詞と
描写が素晴らしく、彼女の成長を見守っていたくなる。
この作品はCloverWorksが手掛けており、
CloverWorksといえば「美麗」な作画で有名だ。
しかし、今作の作画は「美麗」とは違う。
キャラクターはシンプルな線で作られたデザインをしており、
この手の日常アニメらしいキャラクターデザインだ。
作画がすごい!と静止画で見て感じる部分は少ない。
しかし、このどこか力の抜いたキャラクターデザインを
「ぬるぬる」に動かしているのがCloverWorksの凄さだ。
コロコロと変わるキャラクターの表情はキャラの魅力につながっており、
「後藤ひとり」というぼっちな彼女の陰キャぶりやぼっちぶり、
陰キャだからこその反応や表情をコロコロと変えながら描くことで
彼女の魅力にもつながっている。
ギャグ的な作画になったり、真剣な作画になったり、
シーンによってキャラデザが変わりまくる「後藤ひとり」という
主人公の存在がこの作品の肝でもある。
歌詞の部分に関しても「バンド」あるあるが詰まってる。
最初は自分らしく、そのバンドらしく「個性」のある歌詞や曲を作ることが多い。
だが徐々にバンドとして人気が出てメジャーデビューなんてものが見えてくると、
「売れる」ための歌詞作りと曲作りになっていく。
バンド経験者ならば思わず「あるある」と頷いてしまうような要素が
この作品にはちょこちょことあり、
ぼっちで陰キャな少女の成長と「バンド」ストーリーが
非常にうまく噛み合っている。
4人でちやほやされたい
彼女たちの曲は「5話」でようやく完成する。
ボーカルはギターがあまりうまくなく、
バンドとしてまとまりがあるとはいえない。
主人公である「後藤ひとり」も人前での演奏はまだ苦手だ。
でも、彼女は自覚する。一人ではないことを。
一人でチヤホヤされるならネットでギターヒーローで活躍し続ければ良い。
だが、今は一人ではもう満足できない。彼女は知ってしまった。
「伊地知 虹夏」と出会い、「結束バンド」を組み、
バイトをし、多くの人との交流の果に彼女は今何がしたいかを噛みしめる。
4人でちやほやされたい。
そんな彼女の気持ち、決意が固まることで彼女は一瞬のきらめきを見せる。
踏み出した足は決意の証だ。
彼女の中のギターヒーローが、彼女の中のロックが「ステージ」できらめく。
その一瞬の演奏シーンのアニメーションは流石だ。
他の3人が思わず戸惑うほどの超絶技巧をぬるぬるとした
アニメーションで見せながらキャラクターの表情も見せる。
「喜多 郁代」の見た目からは想像できないかっこいい歌声、
「山田 リョウ」の世界を感じさせるベース、
「伊地知 虹夏」の素直で元気なドラム、
そして「後藤ひとり」のボッチで陰キャでロックなギターが合わさることで
「結束バンド」というバンドの個性をビンビンに感じられる。
そんなかっこいいライブシーンを見せられたあとに
後藤ひとりが「ゲロっちゃう」オチもついている(笑)
この作品、作画に関してはシンプルな物が多いのだが、
演出部分でかなり遊んでいる。
積極的に「実写」を取り込んだり、
ぼっちな彼女の脳内を表現するような演出も多く、
演出面での遊びがCloverWorksの実力をもひしひしと感じさせる。
売れないバンドマン
中盤になると主人公はちょっとしたきっかけで
「廣井 きくり」に出会う。
酒に溺れまくりで、常に酔っ払っているような彼女。
だが、主人公にとっては先輩バンドマンだ。
彼女には絶対できないようなことを成し遂げる。
即興で、路上ライブをするなんてことは彼女には絶対できないことだ。
同年代の友達ですらろくにできない彼女なのに、
彼女は年上のバンドマンに出会い、路上ライブをするハメになる。
彼女はまだ「誰かの前」で演奏することに慣れていない。
お客さんを前にして、自分の自信のなさや、
ぼっちがゆえに「誰かに認知」してもらうことの怖さがまだある。
そんな「恐怖」をちょっとしたきっかけで乗り越える。
先輩バンドマンのリードベースで背中を後押しされるように。
そんなライブが「チケット」の売れ行きにもつながる。
たった5枚のチケットですら売れずに困っていた彼女が、
先輩バンドマンと、彼女との演奏を聞いてくれたお客さんに売れる。
初めて友達や家族以外に「チケット」が売れることの嬉しさ、
「誰かに認めてもらう」ことの嬉しさはかけがえのないものだ。
売れたからこそ、ライブを頑張ろうと思う。
バンドをもっと真剣に、もっとみんなで、良いライブにしたいと思うようになる。
バンドを始めライブハウスでのライブをやることの楽しさを
彼女が「じんわり」と噛みしめる表情はかわいらしくも愛おしい。
陰キャ
1クール通しても「主人公」の陰キャっぷりはあまり治らない。
長年のボッチ故に、陰キャ故に、彼女は自己肯定感が低く、コミュ障だ。
それゆえの台詞はかなり生々しく描かれており、
「誰かが自分の家に来る」という出来事でさえ彼女にとっては一大事だ。
彼女の「視線」の描き方も面白い。彼女の視線は「下」に向きがちだ。
彼女にとって「人と目を合わせる」という
行為の難易度の高さを荒らしている。
キラキラな青春映画や、青春恋愛ソングを聞くだけで拒否感が生まれる、
筋金入りの陰キャでボッチな彼女は筋金入りなだけに簡単には治らない。
彼女は決して陽キャなどにならない、
子供の頃からのぼっち、子供の頃からの陰キャは今更治るわけがない。
確かにバンドメンバーと仲良くなっていってはいるものの、
「ぼっち」は変わらないのだ。
同じクラスで彼女に話しかける友人も話しかけてくれる友人も居ない。
バンドメンバーも「友達」のようで「友達」ではない。
どちらかといえば「家族」や「仲間」だ。
1クールを通して彼女のぼっちと陰キャは変わらない。
だがそれでも彼女なりに成長している。
陰キャでも、ぼっちでも、それでいいじゃないかと
彼女がそれを受け入れていき、それが自分らしさであり、
そこに「甘える」のではなく、それを表現する形に変わっていく。
そんな自分を受け入れてくれる、認識してくれる人が増えていく。
最初はバンドメンバーが、次は二人だけのファンが。
徐々に、本当に徐々に「陰キャ」で「ぼっち」な
彼女が多くの人に受け入れられていく。
ライブ
中盤では彼女たちの「初ライブ」が描かれる。
4人になって初めてのライブ、声は震え、テンポは崩れ、いつも通りができない。
練習ではあれほど完璧だったのに、いつもどおりにできない苛立ち。
せっかくの初ライブなのに観客は見向きもしてくれない。
演奏も、曲も、まだまだの彼女たち。
だが、そこに「ギターヒーロー」が舞い降りる。
彼女は長い間、たったひとりでギターを引き続けつけてきた。
「ギターヒーロー」として3万人の登録者がいる、
それを現実でも出せれば多くの人をひきつける
「なにか」を彼女は持っている。
未だに視線はうつい向いたままだ。
見つめるのはただ「己のギター」のみだ。
しかし、自分のためだけではない。
「バンド」としていいライブにしたいからこそ、
彼女は自己表現を全開にギターにぶつけている。
この音の表現も素晴らしい。
緊張によるリズムのあわなさ、ボーカルの声の震え、
そういった「音楽」による表現がきちんとできており、
だからこそより「聞いている」だけで彼女たちの心情が伝わってくる。
音楽自体にもきちんとキャラクターの「心理表現」をさせている。
特にボーカルである「喜多 郁代」さんを演じている
長谷川育美さんの歌声の演技は素晴らしく、
歌いながら歌で演技をするということを両立させている。
敬語
終盤になっても彼女の話し方は変わらない。
同じバンドメンバーにでさえ彼女はずっと「敬語」だ。
「仲良くなる」ということは自分も相手を認め、
相手も自分を認めてくれるという認識があるからこそだ。
彼女は他のバンドメンバーのことを認めている。
だが、自分が認められているか「不安」がある。
だからこそ、いつまでも「距離」がある。
そんな彼女が認められる。
彼女の「ギターヒーロー」であることを知られ、
いつも彼女に助けられていることを自覚し、
「伊地知 虹夏」が彼女を認め、彼女の「ロック」を肯定する。
「私、確信したんだ、ぼっちちゃんがいれば夢を叶えられるって。
だからこれからもたくさん見せてね、ぼっちちゃんのロック、
ぼっち・ざ・ろっくを!」
誰かに「言葉」で彼女を、彼女のロックを認められる。
そう言わずともみんな彼女のことは認めている、
だが、言葉で言わないと彼女はわからない。
8話でタイトルの意味を回収するストーリー構成も素晴らしく、
気持ちのいいぼっち・ざ・ストーリーがテンポよく展開していく。
陰キャでも良い、ぼっちでもいい。
それを「卑下」するのではなく、それを「自分らしさ」と認め、
その自分らしさをこの作品の主人公である「後藤ひとり」は
己のギターで、ロックに表現している。
だからこそ彼女たちと「遊びに行きたい」と主人公が思うようになる。
自分が相手を認め、相手も自分を認めてくれるんだと思ったからこそ、
「友達」として認識できる。
陰キャでぼっちな彼女だからこその心理描写と、
それによるストーリー展開やキャラクター同士の関係性の描き方が
生々しさすら感じる。
ロックとはかつて「不良性」のようなものがあった。
どこか悪そうで、何ならドラッグでも決めてそうな人たちが
社会や何かに対する「反逆」の歌詞を刺激的な音とともに伝えていた。
それがかっこよく見えてしまい、ロックという音楽も同時にかっこよかった。
だが、そんな不良性は現代において等に失われている。
今どき、不良などかっこ悪いなど言われる方が多い。
ならば現代の「ロック」とはなんなのか。
1話の冒頭で主人公がどこぞのミュージシャンの言葉に刺激され
ギターを始めたように、この作品の視聴者も「ロック」の本髄を感じていく。
バンドは陰キャでも輝ける、陰キャの輝きこそ「ロック」だ。
今流行のバンドメンバーでさえ、
音楽をやっていなければヒゲメガネだったり、きのこ頭の
陰キャでしか無い。
だが「ロック」で自身を「自己表現」してるからこそ
かっこよく、輝いて見える。
現代のロックとはなんなのか。
ぼっちとはロックなのでは?陰キャとはロックなのでは?と
この作品は伝えたいのかもしれない。
青春の舞台
彼女は中学生の頃から頭の中で1000回以上文化祭ライブをしている。
だが中学生のときに友達はおろか、バンドすら組んでない彼女には
無理な話だった。だが、今は違う。
バンドを組めた、バンドメンバーとも仲良くなった、
ライブも何回している、だからこそやれるかもしれない。
そんな思いはあれど一歩を踏み出せない。
普段のライブハウスのライブとは違い、多くの学校の生徒の前で
普段は誰ともはなさないような彼女がライブをする勇気はない。
そんな彼女の思いを「先輩バンドマン」が押してくれる。
大勢の人たちの前で「結束バンド」として演奏をする。
見ている側が不安になってしまうほどだ。
彼女はきちんとできるのか、どこか「親心」のようなものを刺激される。
それと同時にこの作品を見てる人の多くは彼女に「自分」を、
もしくは「過去の自分」の影を見てしまう。
ボッチだった自分、陰キャだった自分、音楽をしていた自分。
全く同じというわけではない、だが、
陰キャだった、ぼっちだった人たちの過去を刺激してくれる。
だからこそ、自然と陰キャでボッチな視聴者は彼女を応援してしまう。
あの頃の自分が一歩踏み出せなかった一歩を、
彼女はゆっくりと踏み出そうとしている。
一人では見えなかった景色
最終話の文化祭ライブ、相変わらず「主人公」はうつむいている。
ボーカルはかつてのような声の不安定さはなく、
ベースもドラムもリズムを取っている。
だが、どこか「ギター」だけは自身がなさげだ。
緊張と不安が入り交じるギターは彼女の自身のなさを音で表現している。
そんな緊張の糸という名の「弦」が切れてしまう。
ただでさえ文化祭の舞台という大舞台で緊張と不安が入り混じってる中での
トラブル、彼女一人では解決しようもない。
だが、彼女はもう「一人」じゃない。
彼女の横にはボーカルとギターの「喜多 郁代」がいる。
遅れて結束バンドに入ってきた彼女は
主人公が居なければこのバンドには戻ってこなかっただろう。
そんな主人公への恩、主人公を信じ、
彼女の「かっこよさ」を知っているからこそ「アドリブ」でカバーする。
たった一人では乗り越えられなかった、
たった一人では諦めてしまったかもしれない。
もう彼女は一人じゃない、ひとりじゃないからこそ彼女は
「自分」を表現できる、自分を認識してもらえる。
一人では見えなかった景色、それを彼女が噛みしめるさまは涙腺を刺激されてしまう。
彼女のライブシーンの最後の姿は「ロック」そのものだ(笑)
空気が読めない陰キャだからこその行動は
この作品らしい「オチ」にもなっている。
1クールで「文化祭」という良い区切りがついており、
彼女たちのバンド活動はこれからだ!という感じですっきりと終わっている。
ぜひ2期を見たいところだが、もしなくても問題ない区切りがきちんと
ついている作品だった。
総評:ぼっちとはロックと見極めり
全体的に見て「陰キャ」や「ぼっち」といったものを芯に捉え、
そこに「バンド」要素を組み合わせることで「ロック」な作品になっている。
主人公の「後藤ひとり」の陰キャっぷりは凄まじく、
被害妄想、自己肯定感の低さがリアルかつ生々しい陰キャを表現しており、
そんな彼女が少しずつ成長していく物語がストレートに描かれている。
この作品はあくまで「後藤ひとり」の物語だ。
しかしながら結束バンドのメンバーの一人ひとりに愛着を持てるようになっており、
「後藤ひとり」をバンドに誘った「伊地知 虹夏」のバックボーンや、
彼女からギターを教わった「喜多 郁代」の成長など、
一人ひとりの物語もきちんとあり、それが主人公の成長にもつながっている。
決して「陰キャ」であることを否定しては居ない。
それは彼女の個性であり、それを彼女自身が自覚しながら、
「自己肯定感」を高めていきながら、
徐々に、本当に徐々に自分自身のパーソナルスペースを広げていっている。
そこにあるのは「音楽」だ。
音楽というつながりで他者とつながりながら、
彼女は「自己肯定感」を高め、それを自身のギターにぶつけている。
1話では人前では上手に弾けなかった彼女が、
最終話では学園祭ライブという場でソロパートをやれるほど成長している。
その成長の過程が本当にじっくりと描かれている。
最初は誰かと目を見て話すのすら危うかった彼女が、
バンドメンバーとの距離を徐々に縮め、ときに先輩バンドマンに背中を押され、
たったひとりでは見れなかった景色を見ることができている。
陰キャでも良い、ぼっちでもいい、彼女には「ロック」があり、
そんな「ロック」を通した仲間がいる。
過去の不良性を含んだロックから、
陰キャという、社会不適合者ともいえる存在の表現としての
ロックがこの作品にはある。
バンドをやっている人たちの中には酒や煙草に溺れるものも居る、
コミュ障で、どこか空気が読めない人もいっぱいいる。
いわゆる「クズ」な人もいっぱいいる。
そんな彼らが唯一、社会に認められ、自己を表現する手段が
「ロック」なのだとでも言いたいような作品だ。
音楽による表現も面白く、きちんとキャラクターの心理状態が
「演奏」自体にも反映されており、
それが最終話の演奏でも生きてくる。
彼女たちはまだまだアマチュアのバンドだ。
そんな彼女たちが不器用に、だが成長していることを「音楽」という
音の表現でも感じさせてくれる。
作画のクォリティも、キャラクターデザイン自体はシンプルであり、
きらら系作品でありながら「萌え」な要素はかなり薄い。
女の子女の子した可愛らしさではなく、
キャラクターの根本からにじみ出るような魅力を含めたキャラクターを
シンプルな線で描きつつも、表情の変化やギャグ的な演出で
アニメーションとしての面白みも感じさせている。
ただギャグシーンに関しては若干好みが分かれるところかもしれない。
パロディギャグも多く、後半はかなり、そのパロディやギャグ要素も
強まっている部分が多い。
彼女の顔芸にちかいギャグ表現など、個人的には好きなのだが、
ギャグに関しては好みが分かれるところだ。
長々と語ってきたが一言で言えば完成度の高い作品だ。
作画、音楽、キャラクター、ストーリー。
好みはあるかもしれないが、「陰キャ」で「ぼっち」な
「あなた」には刺さる作品かもしれない。
個人的な感想:自己投影
この作品の主人公の陰キャっぷりやぼっち感は本当に生々しい。
演じている「青山吉能」さんの演技も本当に素晴らしく、
彼女の「キョドる」演技の数々はリアルすぎて笑ってしまうほどだ。
逆に言えばこの作品は「陰キャ」か「ぼっち」な人にしか
刺さらない作品なのかもしれない。
どこか人と接するのが苦手で常に人の目線から逃れようと
視線をそらしてしまい、誰かと仲良くなりたいとは思いつつも、
自分からは踏み出せない。
そんな自分自身の中にあるなにかをこの作品の中の主人公や
キャラクターに感じ、ある種の自己投影が生まれ、
この作品への没入感が強まってしまうような印象だ。
そこまでの没入感と自己投影が生まれるのは
アニメとしてのクォリティが高いからこそだ。
売上的に見れば2期がある可能性は高いと思うが、
2期があるならば期待したい作品だ。