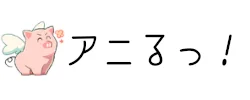評価 ★☆☆☆☆(15点) 全111分
あらすじ 叔父クローディアスへの復讐に失敗した王女スカーレットは、「死者の国」で目を覚ます。そこは、略奪と暴力がはびこり、力のなき者や傷ついた者は「虚無」となって存在が消えてしまう世界だった。 引用- Wikipedia
作家性の搾りかす
本作品は細田守監督によるオリジナルアニメ映画作品。
制作はスタジオ地図
監督
ネタバレ有りのレビューに入る前にネタバレ控えめのレビューを行っていくが、
私は細田守監督との相性が良くない。
サマーウォーズのころからしっくりとこず、
長年、そのしっくりとこないものを言語化できずにいたのだが、
そのしっくりとこないものを本作品でようやく言語化できそうだ。
細田守監督は「ポストジブリ」と呼ばれていた監督だ。
バケモノの子、未来のミライあたりまでは確かにその傾向が強く、
世間や業界の声に監督も応えようとしたのだろう。
しかし、ジブリ、宮崎駿監督が描いてきたものと細田守監督が
描こうとしているものは方向性が違う。
基本は現代を舞台にしつつ、そこにSFやファンタジー的要素が絡み合う。
あくまで主体は現代劇だ。
それなのにポストジブリ的なものを求められるからこそ、違和感が生まれ、
監督自身が脚本を手掛けてからは、その脚本のクオリティの問題もあるが、
監督自身の「作家性」というものも限界を迎えていた。
バケモノの子で作家性と呼ばれるものは限界だったのかもしれない。
未来のミライでは自身の家族、息子から着想を得て大失敗し、
竜とそばかすの姫は代表作であるサマーウォーズを
自らの手で焼き直そうとして失敗している。
搾りかす
もう何も残っていない。
バケモノの子の時点ですでに終わりかけていたのに
自身の息子、自身の代表作を作品にし、もう何もなかった。
だからこそ今作は既存の作品である「ハムレット」を題材にしている。
細田守監督自身がもう「何が面白いのか」がわかっていないのではないか、
そんな思いすらこの作品からひしひしと感じてしまった。
終盤など、もしかしたら細田守監督自身の叫びだったのかもしれない
「私の人生はなんだったんだ」
虚無という言葉が何度も使われる。
個性を出そうと、オリジナル性を出そうと、求められたものを作り上げようとした。
だが、結局、どれもできなかった。
自身が最初に監督として手掛けたデジモンやサマーウォーズのように
ある種の原点回帰のように監督は「原作」を求め、
結果的にたどりついたのがハムレットだ。
だが、ハムレットをそのままやることは許されない。
結果的に原作改変と魔改造でこの作品は出来上がっている。
もはや苦肉の策のような作品だ。
ハムレット
ハムレットはシェイクスピアの戯曲であり、
簡単に言えば復讐劇だ。
父が急死し、叔父と王妃が再婚したかと思えば、
父の亡霊が現れて自身は叔父に毒殺されたといい、
主人公であるハムレットは復讐を誓う。
主人公が悩みあがきながら「生死」について考える。
ハムレットでは有名な台詞がある
「生きるべきか死ぬべきか」
それを問うような復讐の物語だ。
この作品もそこは変わらない、生きることや死ぬことについて考えるのだが、
問題は物語の舞台が「死者の国」であることだ。
下地には確かにハムレットがあるのだが、
そこから魔改造した結果、異世界冒険ハムレットになっている。
作画
作画自体は本当に素晴らしい、今作はCGでのシーンが多く、
キャラクターデザインも今までの細田守監督作品とは少し違う。
そういった面でもキービジュアルだけ見ると細田守監督作品と
分かりづらい部分もあるのだが、そういった「らしさ」を捨てた
キャラクターデザインはあまり印象には残らない。
日本のアニメ映画は最近「ChaO」や「トリツカレ男」など
癖のあるキャラクターデザインのアニメ映画がちらほらでてきており、
この作品もかわいいともかっこいいとも言えないキャラクターが多く、
細田守監督作品らしい「少年」や「ケモナー」要素は一切ない。
未来のミライで強引にケモナー要素をぶち込んできた細田節はどこへやらだ。
ただ本当に映像は素晴らしい。
序盤、現世の16世紀のデンマークの風景、
城の中の装飾品、絨毯や洋服に到るまでこだわりまくった背景美術があり、
序盤を過ぎて訪れる死者の国では基本的に「廃校した世界」なのだが、
砂や岩肌、雷、終盤では噴火するマグマや海など、自然の描写も圧巻だ。
戦闘シーン
今作では何回か戦闘シーンがあり、基本的に「剣戟」で行われる。
重厚な鎧をまとった敵に主人公であるスカーレットが
短剣一つで華麗に身をこなしながら戦う姿は見惚れるほどの
アニメーションがあり、凄いという言葉しかでてこないほどだ。
CGだからこその滑らかな動きとカメラワーク、
計算された肉体の動かし方から生まれる華麗なアクションは
見ていて爽快感があり、一歩間違えば死んでしまう中で、
多勢に無勢を強いられながらも戦うスカーレットの姿は美しい。
馬に乗りながらのアクション、弓や槍など、
戦闘がパターン化しておらず、シーンによって異なるシチュエーションで
きちんとそのシチュエーションだからこそのアクションを見せてくれる。
一流のアニメーションだ。本当にここだけはいつも素晴らしい。
だが脚本家である「細田守」がいつも邪魔をする。
ここからはネタバレを含むレビューとなりますのでご注意ください。
死者の国
序盤でスカーレットは父の復讐に失敗し、
叔父に毒をもられて死者の国に訪れることになる。
この死者の国に関しては冒頭で説明がある、
バケモノの子のころから変わらず世界観の説明のヘタさは相変わらずだ。
この死者の国は生と死が交わった場所で、過去も未来もない。
この場所で再び死ぬと体は塵となり「虚無」になるという設定だ。
それを冒頭でわざわざ説明してくれる。
主人公であるスカーレットの目的はシンプルだ、
現世で果たせなかった復讐を果たすために、まだ塵になっていない
復讐相手である叔父をこの世界で見つけ出し、虚無らせる。
シンプルなのだが、どこかゲーム的なストーリー展開だ。
純粋なお姫様であるスカーレットはすぐに騙されそうになったりするが、
途中で「令和の男」と出会う。
彼は自分が死んだことを自覚してない看護師であり、
そんな令和の男だからこその価値観でスカーレットと会話を繰り広げる。
この令和の男こと「聖」は意味不明の極みであり、
自分が死んだということを自覚していないのはまだいいのだが、
「よりによって看護師の俺が!? 」
と意味不明なセリフを吐く。
ツッコミどころ
この死者の国の設定がふわふわしている。
前作の「U」もそうだったが、細田守監督は用意する世界観の
「外側」は魅力的なのだが、中身がスカスカだ。
だからツッコミどころが生まれてしまう。
死者の国には過去も未来も国も関係なく死者が存在している。
それはわかる、だが、明らかにスカーレットと同じ時代の人が多く、
逆に「聖」のような現代人はメインキャラには聖以外おらず、
モブキャラにもいたかもしれないが、
日本の現代人のような姿のキャラはほとんどいない。
死ねば塵になるという設定なのはわかるが、
一応「喉も渇く」うえに「食料」も必要なようだ。
体の仕組みのようなものは現世とほぼ変わらない。
そうなると食糧問題が発生する。
死者の国は荒廃し、砂漠のような場所も多く、
森や自然などが描写されることはあまりない。
それなのに死者の国の住人が食べるものに困っている姿はない。
死者の国に「ラクダ」や「馬」もおり、
そうなると「犬や猫」などがいてもおかしくないのだが、
そういった描写はなく、こういった世界観の細かい描写や
設定を見せてくれないためツッコミどころや違和感に繋がっている。
戦闘シーンで銃を使用することもあるのだが、
おそらく死んだときに身につけていたものはそのまま死者の国へ
持ち寄れるのだろう、だが、そうなると弾丸には限りがあるはずなのだが、
そういった事を気にする描写はない。
死者の国、死後の世界のはずなのにまるで現世のような感覚で
水を飲み、料理を食べ、拳銃をぶっ放すことに違和感しかない。
挙句の果てには死者の国に「城」まであり、
主人公の復讐相手が玉座に座っていたりする。
この城はどうやって死者の国に建てたのか、
復讐相手の叔父の王が未練として城とともに死者の国にきたのだろうか…?
そういう疑問やツッコミどころ、違和感があまりにも多い。
序盤は死者の国の人口もスカスカな感じがあるのだが、
目的の場所まで行くともう国レベルの人数がおり、
溢れ返っており、挙句の果てに空にはドラゴンもいる。もうわけがわからない。
生きるか、死ぬか、それが問題だ
スカーレットは復讐に夢中だ、父の処刑に携わった人物が
目の前に現れれば絶対殺すガールとなりつっかかっていく。
だが、そんなスカーレットに対して「令和の男」である看護師は
命は大切だ!殺すな!と現代的な価値観で彼女に接する。
16世紀の価値観と21世紀の価値観、そこには大きな開きがある。
だが、21世紀の価値観でスカーレットに接し続けた結果、
スカーレットは徐々に不殺になっていく。
その変化があまり納得行かない。
彼女は幼い頃から修練をつみ、
男相手でも立ち向かえるほどの力を手に入れ復讐に人生をかけている。
そんな復讐を遂げることができずに死んでしまったことへの後悔もあり、
死んでなお復讐を果たそうとしている。
長い間、復讐に人生を捧げてきた人物がぽっと出の令和の男に染まっていく。
「恋愛」というものすらしなかった彼女が、
高身長イケメンに惚れて価値観がかわっていく姿は
見ていて痛々しいものがある。
「細田守監督」の弱点でもある女性キャラの描写の下手さ、
キャラクターの心理描写の下手さが今作でも浮き彫りになる。
彼女が人生をかけた復讐心が揺らぐほどの関係性の構築、ドラマが無い。
「聖」がやったことといえば彼女を弓矢で少し助けたり、
途中出会ったキャラバンの治療をして謎の踊りを披露したくらいだ。
最終的にはキスまでするのだが、そこまでの関係性になったのか?と
思うほど浅い。
歌い、踊るよー
その関係性、復讐心の変化のきっかけとなるのが
「可能性」の世界の描写だ。
中盤あたりで主人公と聖がキャンプファイヤーをヤッてるときに、
聖が彼の時代で流行ってる謎の歌を歌い出す。
それをきっかけに本当に唐突に主人公の意識がタイムスリップする(笑)
あまりにも唐突な展開で意味不明だが、現代の渋谷の前で
「聖」や街の人達がフラッシュモブのごとく気持ち悪い笑みを
浮かべて踊っており、そこには髪を切った「スカーレット」も参加している。
これは予告編などでも流れているシーンだ。
そんな場面を飛ばされた意識で見ているスカーレット、
渋谷で踊る自分自身を見て「これはもう一人の私だ!」と
意味不明なセリフを吐く。何を持ってもう一人の私と
スカーレットが感じたのか、本当にわからない。
ようは「楽しそうにしている自分」を見て
「復讐心」を揺らがせたかったのはわかるが、
唐突すぎる展開とセリフのせいで意味不明さだけが残る。
前作は「歌唱シーン」を評価する人が少なくなった。
だからこそ本作でもそういうシーンを入れようとしているのはわかるが、
渋谷で歌い踊り狂う意味もわからなければ、ラストで唐突に歌い出す
必要性もない。歌という要素の使い方があまりにも下手だ。
テーマ
復讐というものに人生を掛ける意味、
生と死の問答を、看護師という生と復讐姫という死で描こうとしているのはわかる、
わかるが、それが面白さになっていない。
この作品でやりたいことはシンプルだ。
「復讐の連鎖を断ち切るためには許すことが必要」
もう何度目だといわんばかりの普遍的なものでしかない。
ガンダムSEEDしかり、ありとあらゆる作品で描かれた憎しみの連鎖というものを
やろうとしているのはわかる、憎しみに囚われたスカーレットが
聖と出会い、復讐相手の命を一切奪わない。
最終的に1番復讐したい「叔父」に対してもそれは同じだ。
父の遺言でもある「許す」という言葉の意味を理解し、
自分を他者を許すことで憎しみに囚われた不毛な人生ではなく、
幸せな人生を送れる、それを理解した彼女は復讐をやめる。
そういったストーリーを描きたいのはわかるが、
そこに至るまでの過程の描写が甘く、
結局、最後は謎ドラゴンの天誅で終わるのも意味不明でしかない。
このドラゴンもいい所で現れては死者の国の人たちに雷を落とし、
なにがしたいんだと思う要素の1つだ。
最後でどんでん返しとまでは行かないものの、伏線回収的な要素もあり、
一応はハッピーエンドでは終わるものの、
スカーレットと聖の「生きたい!」という言葉を連呼するシーンは
ギャグのようにしか見えず、感動させたいのはわかるが、感動できず
むしろ笑いになってしまうようなズレたラストシーンになってしまっていた。
総評:果てしなきスカスカ虚無映画
全体的に見てスカスカな作品だ。
映像という見た目のクオリティはものすごく高い、
だが、その中身がスカスカすぎて空虚な虚無になっている。
もう、細田守監督に描きたいものはないのだろう。
「作家性」というものが失われ、ハムレットを魔改造したストーリーを
やったはいいものの、ツッコミどころのある世界観や
前作で受けたからと歌唱シーンを入れたり、浅いキャラ描写と心理描写で
ドラマを作りきれておらず、見ていても感情が揺り動かされない。
テーマと言われるものの
「復讐はやめて相手を許そう、憎しみの連鎖を断ち切ろう」
的なもうこすりまくられた浅い内容でしか無く、
それができれば殺人も戦争も起きないんだよと
あたりまえのこと、どこか反戦主義な左翼的なニュアンスも感じる。
「芦田愛菜」さんの演技もやや厳しい部分があり、
特に叫びなど感情を露骨にあらわにするシーンではかなり違和感を産んでいる。
スカーレットというキャラクターと彼女の声のミスマッチさもあり、
余計にその違和感がキャラへの没入感を拒絶させてくる。
終盤の生きるか死ぬかみたいな問答も、
ハムレットを題材にしたからこそなのはわかるが、
「宮崎駿」や「庵野秀明」が作品の中で見せてくれた生や死に比べて
あまりにも軽い、だからどうでも良さが強くなっていき
説教臭さだけが強くなる。
作れば作るほどつまらなくなる、こんな監督はめったにいない。
次回作というものがあれば、一体どんな作品になるのか、
一周回って興味すらでてきてしまう監督だ。
個人的な感想:失われたもの
細田守監督作品が好きだった人も見放すレベルだろう。
過去作では作家性を感じていたのに、今作ではそれすらなくなってしまった。
その象徴が「ケモナー」要素と「ショタ要素」の排除だ。
細田守監督はこの作品を楽しく作れたのだろうか、
本当に面白いと思って作れたのだろうか、その答え監督の好きな要素の排除で
現れているかのようだ。
私は演出家としての細田守さんは大好きだ。
彼にしかできない「空気感」によるキャラ描写は本当に素晴らしく、
どこか異質ささえ生まれるのが細田守という演出家だ。
そんな異質さを監督として発揮できていない、
その「才能の無駄遣い」が私が細田守監督作品と相性が悪い最大の原因なのだろう。
前作までは少なくとも演出家としての細田守らしさ、
細田守監督の作家性のようなものを感じたからこそ、
不満点で苛立ちを感じていた。だが、今回はそんな苛立ちすらない。
あのころの演出、あのころの作家性が失われてしまった。
確かにアニメーションのクオリティは高い、
だが「細田守監督」らしさはあまり感じなかった。
ずっともったいないと思っていたものすらなくなってしまったことで、
本作品では「喪失感」すら感じてしまった。
本当に残念だ。