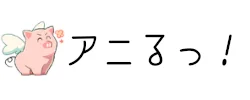評価 ★★★☆☆(45点) 全119分
あらすじ 多々良と百秋坊が「人間界(渋谷)に生きる少年(蓮またの名を九太)とバケモノ界(渋天街)に生きるバケモノ(熊獣人の熊徹)」の人生を語る物語。 引用- Wikipedia
上滑り脚本
本作品は細田守監督によるオリジナルアニメ映画作品。
制作はスタジオ地図
宗師
この世界には化け物たちが住む街がある。
その街の王、長たる存在は「宗師」とよばれ近い内に神になるらしく、
新たな「宗師」を決める必要があり、二人の候補がいる。
映画の冒頭からそんな「説明」を聞かされる。
この冒頭の説明の下手さですべて察してしまう。
本作品から細田守監督だけで脚本を手掛けている。
前作までは「奥寺佐渡子」氏とともに手掛けていたが、
本作品は細田守監督だけだ。だからこそ下手だ。
アニメの中で自然に舞台や世界観を説明するのではなく、
冒頭で1から10まで世界観を説明してしまうのはシンプルにつまらない。
オリジナルアニメ、映画に限らずオリジナルの作品は
「世界観」の説明をどうするかが重要だ。
その説明を見せるのではなく言葉で全て片付けてしまっており、
冒頭から脚本の下手さが際立っている。
一人
主人公は母をなくしたばかりの少年だ。
父親と母親はだいぶ前に離婚しており、
親戚が彼を引き取ろうとしたものの、親戚は彼を「跡取り」としかみていない。
家を飛び出した彼は一人町中を彷徨っている。
そんな彼が「バケモノ」と出会う所から物語が始まる。
冒頭のナレーションによる説明は気になるものの、
細田守監督らしい「影」のある人物描写、そして街の中をひとり彷徨う
少年がバケモノの国に迷い込む流れはどこかホラーな雰囲気が漂っている。
孤独な少年が抱える怖さや不安が「アニメーション」のなかで
きちんと演出されており、これぞ演出家・細田守といわんばかりだ。
親を失った少年と、弟子をとることがなかった熊徹、
不器用な二人が不器用な不思議な親子関係を構築していく。
熊徹は孤独だ、彼は「宗師」 候補として誰からも応援されず、
もう一人の候補のほうが圧倒的に人気だ。
実力においてももう一人の候補のほうが上だ。
そんな孤独な熊徹だからこそ、思わず主人公は応援してしまう。
同じ孤独を抱えるものだからこそだ。
師弟
熊徹はひたすらに不器用だ、主人公である九太を弟子に取るものの、
「教え方」を誰からも教わったことがない熊徹は教えることができない。
師匠としては半人前どころか素人だ。
そんな不器用な師匠と弟子が各地を旅をしながら学んでいく。
「強さ」とはなんなのか。
熊徹の強さを学ぶために彼は「真似」をするところから始まる。
まるで寿司職人の修行のごとく見て学ぶ、
父親も母親もいない彼にとって、徐々に熊徹がもう一人の親になっていく。
この日常の描写は微笑ましく、学び、吸収していく九太を
周囲が認めるようになっていく。
熊徹自身も弟子を取ったことで自らを学び直し、
優秀な師匠に「宗師」 候補 になっていく
スタジオ地図の温かみのある作画と細田守監督の空気感の演出が
見ているうちに心地よささえ感じさせてくれる師弟関係を描いている。
時間はあっという間に流れ九太は17歳になる。
ここにいたるまで1時間ほどの尺を使っており、
やや物語としてのテンポは悪い。
細田ワープ
そんなゆったりとした前半から後編で物語は一変する。
九太が何の前触れもなく人間の世界に戻り、
図書館に侵入し、そこで出会った女の子と仲良くなる。
あまりにも展開が唐突すぎて途中で別の作品が始まったかと思うほどだ。
これは後の細田監督作品でも同じだが、
急に場面が飛ぶことがよくある。
何の前触れもなく場面が転換し、さっきいた場所からは
想像ができないような場所に飛ぶ。
これを細田監督は自身の脚本でよくやりがちだ。
小説版などではそこになぜ居たのかという過程が描かれてることもある。
この作品でも小説では
「久しぶりに人間界へ戻った九太は、
街中に溢れるおびただしい数の文字を見て吐き気に襲われた。
文字を強制的に浴びるのはもうたくさんだ。
どうせなら自分の見知った文字がいい。そうすれば、
子供の頃の感覚も少しは取り戻せるかもしれない」
と書かれている、書かれていても図書館にいたのは納得できない説明だが、
納得できない説明すら省かれて瞬間的に移動するため、
まるでダイジェストのようにシーンが飛ぶような感覚になる。
私はこれを細田ワープと名付けた。
恋愛要素?
そんな女の子「楓」を助け交流が始まる。
なんでそういう展開になるんだ?と思うほど急な展開であり、
いままで知らなかった人間の世界のことを学びながら、
バケモノの世界での日々を送りつつ、楓との逢瀬を重ねていく。
意味がわからない(苦笑)
この後半の展開の意味不明さはぶっ飛んでおり、
例えば「千と千尋の神隠し」で主人公が現世に帰って
イケメン美少年と日常を送りながら湯屋で働いていたら
「そのシーンいる?」となってしまうのと同じだ。
主人公が知らなかった世界のためのキャラなのはわかる、
ろくに人間の世界に行くことがなかった主人公が
新しい世界を知る切っ掛けになる、それだけのためのキャラだ。
終盤でも肝心の所でしゃしゃり出てくるため、シンプルにうざい。
主人公に対して恋愛感情が有るのかないのかもよくわからず、
主人公が旧友と対峙し戦っている間にもしゃしゃりでてきて、
旧友のことなど一切知らないのに正論を振りかざす。
シンプルにうざい。
父
そんな人間の世界の物語になると急に面白みが薄くなる。
本当の父親と再会したりする。
前半に比べて色々なことが起こるものの、色々なことが起こる割には
それが面白みには繋がらない。前半の修行シーンのほうがよっぽど面白く、
急にしけったせんべいのごとく歯ごたえが無くなる。
急に父親と再会し、急に父親と暮らそうと提案され、
二人の父親の間で悩んでると九太の
心の闇が成長していく。
何もかもが急だ。急展開で話についていきづらい中で、
バケモノの国の「一郎彦」が急にブチギレてハラパンしてくる(笑)
彼の中にも闇が生まれつつあり、それをみた九太が
「なぜあいつにも俺と同じものが..」というのだが、
誰がどう見ても一郎彦は人間だ。
彼が幼少期の頃からバケモノの国ではあり得ない
「獣耳」のついたフードを被っており、
見ている側からすれば露骨人間であることは分かる。
周囲がなんで気づかないか不思議なレベルだ。
師弟
それでも師弟の物語としては悪くない。
「宗師」 候補同士の戦いで熊徹が不利になる中、
でていった九太が帰ってきて応援することで彼は勝利を掴む。
まるで稽古をつけるように、二人の間には見えない絆が生まれており、
そんな絆が勝利を掴む。
この結果自体は本当に素晴らしい、だが、
そこに至るまでの過程で人間界での出来事がノイズにしかなっておらず、
急に「一郎彦」が心の闇を暴走させ、熊徹をぶち殺す。
思わず「えぇ…そういう展開になるの?」と思うほどの
展開が巻きおこる。
細田守監督作品にありがちなことだが、
前半はいいのに、世界観はいいのに、後半で物語の収集をつけることができず、
ゴチャゴチャしてしまう。
「一郎彦」に関しても掘り下げがうすすぎる。
序盤でちょろっと主人公と絡んだくらいで別に親友であるわけでもない。
人間世界の女の話を描いてる暇があったら、
彼の掘り下げをもう少しやっていれば違ったかもしれない。
だが、それができないのが細田守だ。
クジラ
闇に囚われた一郎彦は終盤で人間世界にやってくる。
九太が持っていた小説を拾い「くじら」を認識した彼は
唐突にクジラのバケモノとなる。もう意味不明だ(苦笑)
熊徹自身が付喪神に転生し、九太の力になる。
それは彼の中に空いた穴を埋めるものであり、
彼との8年間の家族の思い出、愛情だ。
それを自覚した彼は自分というものを確立し、
一人の人間に、おとなになる。
この展開自体は本当にいいのに、
急な闇落ちだったり、急なくじらだったり、
明らかにいらないヒロインだったりと余計な要素が邪魔をする。
ラストのふわっと終わる感じも細田守監督らしさであり、
釈然としないものが残る作品だった。
総評:細田守に長編をやらせるな
全体的に見て細田監督の脚本の下手さを如実に感じる作品だ。
人間の世界とは違う世界、師弟関係、親子関係、人間の心の闇、ヒロイン、
色々な要素が散漫に描かれるのだが、どれも深堀りされるわけでもない。
全部が上滑りだ。
面白い部分はある、序盤から中盤までのストーリーは
スローテンポでは有るものの主人公と熊徹の関係性を描いており、
そのまま話が進めばこの作品を素直に受け止めることができただろう。
作画のクオリティも本当に高い。
序盤や中盤での人間の世界でのどこか陰鬱とした雰囲気は
細田節全開であり、敵である一郎彦の憂いを秘めた男性キャラクターの
見せ方は細田監督らしさが如実に現れている。
人間の世界とは違うバケモノの世界の表現もジブリを感じさせるほどだ。
しかし、どれも上滑りだけしている。
序盤の熊徹との旅も、熊徹や主人公以外のキャラ描写も、世界観も、
ヒロインとの関係性も、本当の父との関係性も、すべて
浅いところしか描かれておらず、だからこそ話が進めば進むほど
面白さが失われている。
これは後の作品にも言えることだが、
細田監督は少なくとも長編の脚本をやるには向いていないのだろう。
尺を埋めるためにありとあらゆる要素を追加するが、
そのありとあらゆる要素のすべて、やりたいことを掘り下げきれていない。
面白そうな表面だけしか見せてくれず、深堀りしないせいで物足りなさばかりが残る。
これが短編なら尺も限られ、描ける要素も減るはずだ。
60分くらいの短編映画なら細田監督の本領を感じられるかもしれない。
もう時既に遅しかもしれないが…
個人的な感想:父
細田監督はやはり父の描写がいまいち深く描けない監督なのかもしれない。
本作でも本当の父の描写は浅く、次回作の未来のミライでは
家族の話なのに父親の掘り下げが浅い、
竜とそばかすの姫でも父の印象はあまり残っておらず、
最新作の果てしなきスカーレットでも薄い。
以前のインタビュー記事で細田監督は
「僕は父親とお酒を一緒に飲んだり、語り合ったりする前に亡くなってしまった。父親の存在がその距離感で止まっているんです。居心地が悪い宙ぶらりんの状態、それが作品に出ているのかもしれません」
とおっしゃってるが、まさにそのとおりだ。
父親というものがわからないのだろう。
それなのに「家族」というテーマを描くうえで父親の存在ははずせず、
父親というものをどう扱うのか、その迷いが見える。
それなら父の存在を排除すればいいのに、排除しきれず、
脚本にもミスマッチさが見えてしまう。
本当に不思議な監督だ。